「愚公移山(ぐこういさん)」(愚公山を移す(ぐこうやまをうつす))は、どんなに困難なことでも、こつこつと努力し続ければ、必ず成功するという意味のことわざ・故事成語です。
愚公という老人が、家の前をふさいでいる大きな山を崩すため、家族とともに何年も山の土砂を運び続けたという伝説が由来です。
愚公移山のあらすじ
昔むかし、冀州の南、河陽の北に二つの大きな山がそびえていました。この山々は約350kmにも及び、高さは23,000〜26,000メートルもありました。この2つの山は、太行山と王屋山です。
その北の山のふもとに、一人の老人が住んでいました。年齢は九十歳近く、人々は彼を「愚公」と呼んでいました。南の大山が道をふさいでいるため、愚公の一家は出入りするにも遠回りをしなければなりません。そこで愚公は家族を集め、この二つの山を取り除き、道を通そうと決心しました。
彼は皆に相談して言いました。
「私は全力を尽くして険しい大山を削り取り、道を豫州の南まで通し、さらに漢水の南岸まで達するようにしたい。どうだろうか?」
家族は口々に賛成しました。
ところが妻は疑いを口にしました。
「あなたの力では、魁父という小さな山でさえ削り取れないのに、どうして太行や王屋を動かせるのです?それに、掘り出した土や石をどこへ捨てるのですか?」
皆は答えました。
「渤海のほとりや、隠土の北に運べばよいのです。」
こうして愚公は、担ぎ手のできる息子や孫の三人を率いて山に登り、石を砕き、土を掘り出し、箕やかごに入れて渤海の岸まで運びました。近所に住む京城氏の未亡人の子どもで、まだ七八歳の子も、飛び跳ねながら手伝いに来ました。冬から夏に代わる間に、やっと一往復できるほどでした。
やがて河曲に住む智叟という老人がこの話を聞き、愚公を笑いました。
「お前はもう九十を過ぎ、残りの命もわずか。たとえ草一本動かす力もなくなっているのに、どうして土や石を動かせるというのだ?どうやって二つの山を取り除けるというのだ?」
愚公は深く嘆息し、答えました。
「あなたの言うことも一理あります。私一人の力はたしかに限られています。だが、私には子があり、その子にもまた子が生まれる。子々孫々は限りなく続きます。しかし山は高くなりはしません。ならば、いつか必ず削り尽くせるではありませんか。」
智叟はこれに返す言葉を失いました。
その話を聞いた山の神は、愚公が果てしなく山を削り続けるのを恐れ、天帝に報告しました。天帝は愚公の精神に感動し、夸娥氏という神の二人の息子に命じて、太行山と王屋山を背負って運ばせました。
愚公移山の由来・出典
中国の戦国時代の典籍『列子』湯問編に載せられた説話が由来です。
愚公移山と似た故事・関連語
石の上にも三年(日本のことわざ)
ローマは一日にして成らず(西洋の格言)

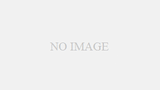
コメント